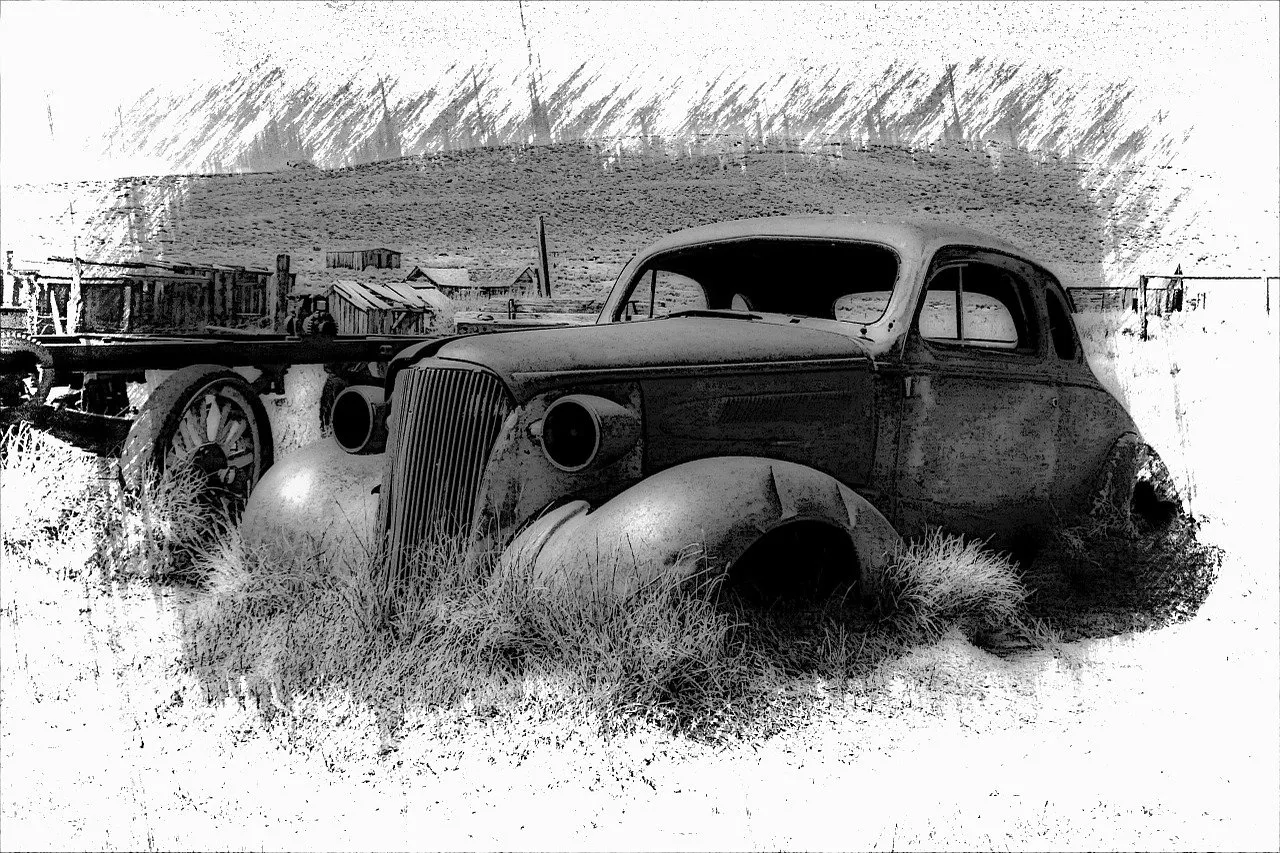
古き良き時代を懐かしむよりも、新しモノ大好きな、ユゲタです。
「レガシー」と聞くと、アンティークや、プレミアものなどの印象が思い浮かびますが、
ITに関して言うとレガシーは、「悪」と判断されることが多いようです。
また、アパレル業界なども、USEDなジーンズなどが高額にやりとりされているようですが、
実際は、ファッションは1年たつと流行遅れとして、来ているだけでも恥ずかしいという意見をよく聞きます。
スマートフォンはiPhoneもAnderoidも、毎年のように、色々な会社から、バージョンアップとされる新機種や、
これまでになかったような機能を備えた、新製品が発売されていて、
これも1年経てば、「もう古い」と判断してしまいます。
そんなレガシーの良し悪しの話で、ユゲタの仕事に直結する「ホームページ」に関するレガシーの話を考えてみました。
ホームページの歴史
ホームページの歴史は、HTMLとインターネットブラウザの歴史でもあります。
HTMLの歴史は、バージョンによるその機能性の遷移で、
インターネットブラウザは、不毛なビジネス戦争による、ユーザー利便性と、HTMLを司るw3cの統制に関わっています。
スマートフォンが登場するまでは、Microsoftのwindows + InternetExplorerの一択で9割以上を締めていて、恐ろしいほどの独創感を突っ走っていましたが、
HTML5とスマートフォンが同じ時期に登場してから、世の中の下剋上が始まったことは今でも鮮明に覚えています。
そんな中、ホームページはというと、インターネットが個人で手頃に普及し始めた1995年からしばらくは、HTMLコードのみを覚えたてのエンジニア予備軍が、
マイホームページとして、table構成または、frameset構成のホームページを作って、ポートフォリオ的な個人情報の発信をしていました。
この頃のホームページには、自分のメールアドレスから、携帯電話の番号まで書き込んでいた事を今でも覚えていますが、凄まじい個人情報漏洩ですよね。
まだ、個人情報保護法という法律もなかった時代なので、致し方ないのも頷けます。
HTMLの発展
HTMLの最初の発展は、スタイルシートの導入だったことを覚えていますが、角丸がcssだけで実装できたことの便利さを今でも覚えています。
当時、box-shadowなんて、神機能でしたよね。
いっぽう、HTMLの黒歴史として、携帯電話サイトというのがありました。
もちろん、スマートフォンではなく、ガラケー時代のwebサイトは、携帯電話で情報発信をするために、
企業は、通信容量を極限まで抑えられるHTML構成でのwebサイトを構築していました。
たまに、それをそのままカンパニーページとして利用している会社などもあり、
この頃はまだあまり、webデザイナーという職も一般的ではなかったため、ホームページも素人でもHTMLさえ知っていればできてしまう時代だったんですね。
でも、携帯電話でFlashが再生出来るバージョンになると、ゲーム業界が活発化して、こぞって、FLASHゲームを大量生産していきました。
greeやdnaなども、ここからがスタートだったことも今でもよく覚えています。
着メロや着ボイスなどは、当時のスタンダードでしたからね。
そして、今でも現役のHTML5の登場で、動画や、色々なコンテンツ・メディアが手軽に構築できて、利用する側もストレスが無くなる時代になり、
スマホと相まって、いつでも誰でも、ググれる時代が到来したんですね。
そんなHTMLはもはや、CSSと組み合わせると、構造体はプログラミングと言っても過言ではない言語に成長したと思いますが、
同時に、これからweb言語を学習する人にとっては、ハードルが高く感じるという事も最近の初学者の人が頭を悩ませている事のようです。
レガシーなホームページとの向き合い方
「ITのレガシーシステムは悪」という考え方は、ユゲタ的には、賛同する反面、長年持ちこたえられるプラットフォームの器の大きさは感動することすらあります。
少し話がそれますが、昭和の時代の家電製品で、今でも使われているものも多くあるのに対して、
平成移行に作られている家電製品は、壊れて買い換えるサイクルのものが多いように感じます。
これは、昔の製品は、使う箇所のみの仕組みしか持っていないため、シンプルで、仮に壊れても、ある程度の知識があれば、簡単に修理できてしまうという事も考えられます。
逆に、最近の家電製品は、そのメーカーのマイクロチップに搭載された組み込みシステムがわからないとうかつに手が出せないものが多く、いわゆるブラックボックス化しているので、
お高いサポート費用を払わないといけないという、不本意なランニングコストがかさむ製品が多く、結果的に「買い替えたほうが安い」という結論になるケースも少なくありません。
レガシーなホームページというと、見た目が古くて、情報も古いものも多いのですが、その中の情報は有意義なものであることもあります。
よく見かけるのは、大学の研究室などで公開されているホームページなどは、インターネット初期の頃から、デザインなどは関係なく、論文掲載や、研究過程のログを表示することが目的なので、
見た目はショボいですが、内容は勝ちのあるものという状態になっているようです。
でも、HTMLに直書きされているそうした有意義なホームページを見た時に、できれば、今どきのデータベース構成にしてあげたいな〜と、考えてしまうのは、
ユゲタのワーカホリックな一面なのかもしれません。
せめてjavascriptで、動的なメニューや要素を増やしてあげたいという、クリエーター魂も同時に発動してしまうんですが、今どきのレガシーではないエンジニアは、
そのぐらいの思考がいいのではないかと、思ってしまいましたね。
特にレガシーページを否定はしませんが、より良いホームページに改築するという改善作業は、運用コストを支払ってでもやる価値はあるかもしれませんね。
運用したくてもできない人もいるかもしれないので、そういうお悩みは是非ユゲタまでご相談ください。
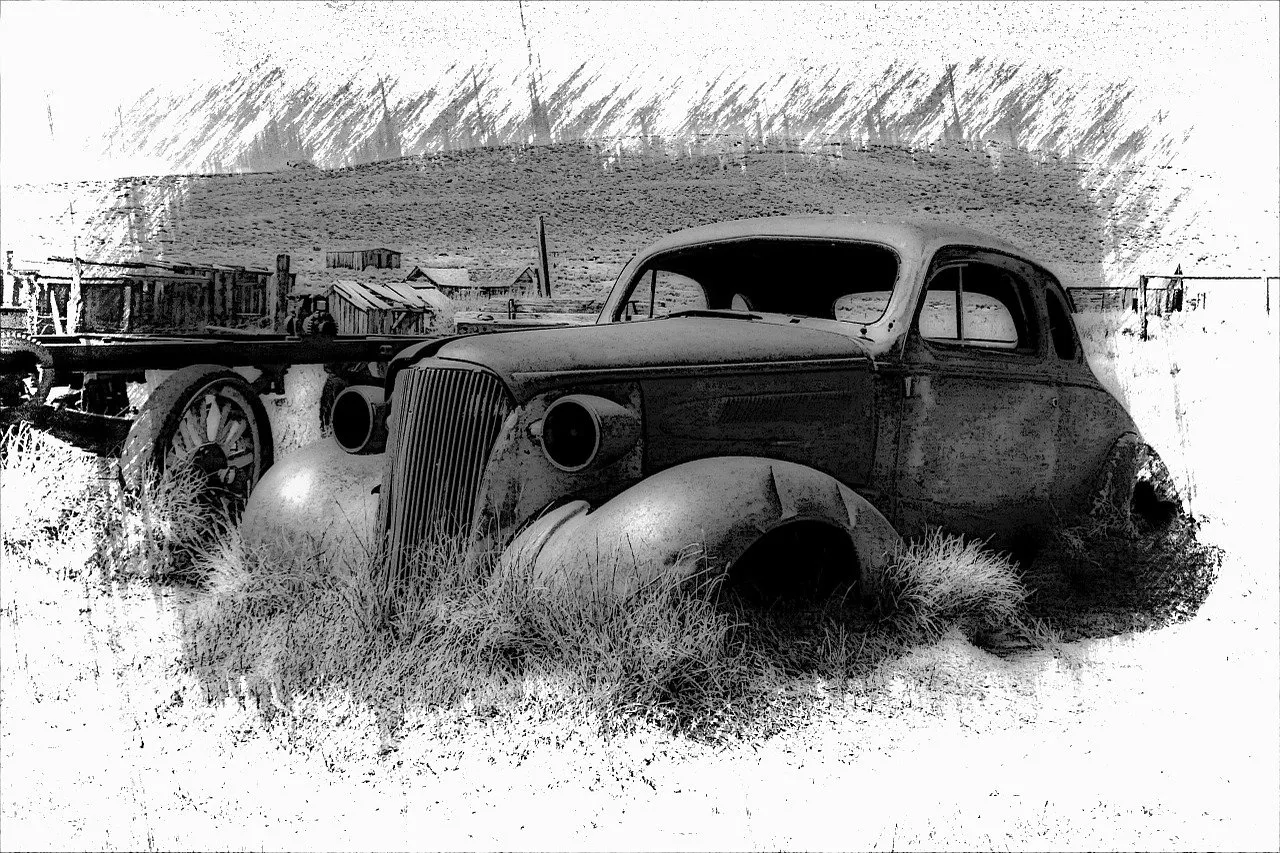 古き良き時代を懐かしむよりも、新しモノ大好きな、ユゲタです。
「レガシー」と聞くと、アンティークや、プレミアものなどの印象が思い浮かびますが、
ITに関して言うとレガシーは、「悪」と判断されることが多いようです。
また、アパレル業界なども、USEDなジーンズなどが高額にやりとりされているようですが、
実際は、ファッションは1年たつと流行遅れとして、来ているだけでも恥ずかしいという意見をよく聞きます。
スマートフォンはiPhoneもAnderoidも、毎年のように、色々な会社から、バージョンアップとされる新機種や、
これまでになかったような機能を備えた、新製品が発売されていて、
これも1年経てば、「もう古い」と判断してしまいます。
そんなレガシーの良し悪しの話で、ユゲタの仕事に直結する「ホームページ」に関するレガシーの話を考えてみました。
古き良き時代を懐かしむよりも、新しモノ大好きな、ユゲタです。
「レガシー」と聞くと、アンティークや、プレミアものなどの印象が思い浮かびますが、
ITに関して言うとレガシーは、「悪」と判断されることが多いようです。
また、アパレル業界なども、USEDなジーンズなどが高額にやりとりされているようですが、
実際は、ファッションは1年たつと流行遅れとして、来ているだけでも恥ずかしいという意見をよく聞きます。
スマートフォンはiPhoneもAnderoidも、毎年のように、色々な会社から、バージョンアップとされる新機種や、
これまでになかったような機能を備えた、新製品が発売されていて、
これも1年経てば、「もう古い」と判断してしまいます。
そんなレガシーの良し悪しの話で、ユゲタの仕事に直結する「ホームページ」に関するレガシーの話を考えてみました。
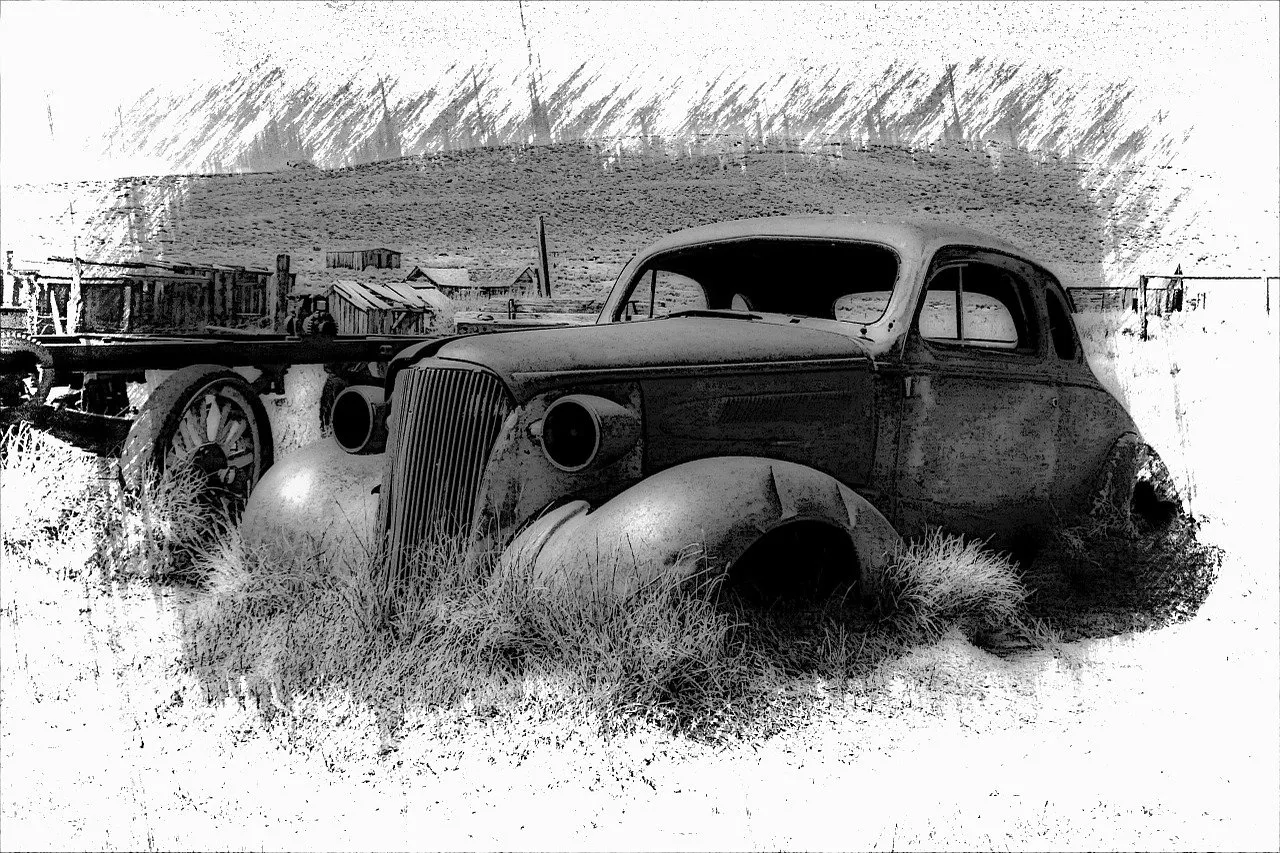 古き良き時代を懐かしむよりも、新しモノ大好きな、ユゲタです。
「レガシー」と聞くと、アンティークや、プレミアものなどの印象が思い浮かびますが、
ITに関して言うとレガシーは、「悪」と判断されることが多いようです。
また、アパレル業界なども、USEDなジーンズなどが高額にやりとりされているようですが、
実際は、ファッションは1年たつと流行遅れとして、来ているだけでも恥ずかしいという意見をよく聞きます。
スマートフォンはiPhoneもAnderoidも、毎年のように、色々な会社から、バージョンアップとされる新機種や、
これまでになかったような機能を備えた、新製品が発売されていて、
これも1年経てば、「もう古い」と判断してしまいます。
そんなレガシーの良し悪しの話で、ユゲタの仕事に直結する「ホームページ」に関するレガシーの話を考えてみました。
古き良き時代を懐かしむよりも、新しモノ大好きな、ユゲタです。
「レガシー」と聞くと、アンティークや、プレミアものなどの印象が思い浮かびますが、
ITに関して言うとレガシーは、「悪」と判断されることが多いようです。
また、アパレル業界なども、USEDなジーンズなどが高額にやりとりされているようですが、
実際は、ファッションは1年たつと流行遅れとして、来ているだけでも恥ずかしいという意見をよく聞きます。
スマートフォンはiPhoneもAnderoidも、毎年のように、色々な会社から、バージョンアップとされる新機種や、
これまでになかったような機能を備えた、新製品が発売されていて、
これも1年経てば、「もう古い」と判断してしまいます。
そんなレガシーの良し悪しの話で、ユゲタの仕事に直結する「ホームページ」に関するレガシーの話を考えてみました。










0 件のコメント:
コメントを投稿