
数字が苦手な人のための本なんだけど、数字が苦手と思い込んでいる人はなかなか手が出しずらいタイトルのようにも思えます。
でも、この書籍は学術的とかの内容ではなく、数学が苦手な人でも、数字を好きになるコツというか、周辺の環境作りについて書かれていて、これまで読んだことのある数学系の本で一番読みやすく、もっともスピード早く読み終えることができました。
書籍紹介
「数字が苦手」は思い込み!
数字と仲良くなった人だけが、話し方、表現力、時間管理力…すべてを手に入れる!
数字センスを身につけて、あらゆるシーンで数字を味方にできれば、自分の伝えたいことが明確に相手に伝わり、表現センス、数値化、時間管理など、ビジネスパーソンの必須スキルが磨かれる!
今日から、あなたの数字との付き合い方が劇的に変わります!
こんなキャッチフレーズで、数字が苦手という人も、「もしかしたら自分も変われるかも・・・」と思うかもしれません。
筆者の「
深沢 真太郎」さんは、「ビジネス数学教育家」という面白い肩書きで、活動されていて、
世の中の人を少しでも数字で楽しめるようにしたいという志を持って、書籍から各種セミナーや講演など、幅広く活躍されている方です。
レビュー
★★★★☆
それぞれのChapter、各章に、いろいろな数字遊びや、計算しずらいフェルミ推定の数字についての根拠サンプルなどが書かれているんですが、
非常に丁寧に解説してくれているので、わかりやすい!というか読みやすい!という感想です。
数字が苦手な人が、数字を好きになる入り口に立てることは理解できたのですが、個人的にはもう少し数字遊びのバリエーションなどが数多く書かれているといいかな〜という物足りなさを感じました。
ページ数が少なかったり、スペースを開けた文字数などによって、全体的なボリューム自体がもうちょっとあってもよかったな〜と思います。
学習ポイント
1. 数字センスのある人の特徴
数字の苦手な人は、%の扱いが苦手だそうです。
150円の商品を、「10%割引き」と「15円引き」とどっちがわかりやすいかは、明確ですよね。
%をすぐに数字に置き換えられるというのは、数字が得意な人の特徴です。
100人の人のうち、「上位8%の人」と言われて、「12人ぐらい」とすぐに頭に浮かぶかどうか・・・
「視聴率17%」と聞いて、大体6世帯のうち1世帯が見たテレビ番組と考えられるか・・・
「投票率33%」は、3人に2人が投票した選挙・・・
こんな数字の置き換えができるかどうかで、数字が得意か苦手かの分かれ目になるようですね。
2. 数字センスをモノにする方法
数字センスがある人の見分け方で次のような問題が書かれていた。
ある仕事が、部下のAさんにお願いすると2時間で終わる。
その仕事を、部下のBさんにお願いすると4時間かかってしまう。
では、AさんとBさん同時にやらせたら、どのくらいの時間がかかる?
この質問に対して、二人で一緒にやるんであれば、仕事を山分けするので、中間地の
3時間なんじゃないか?
という人は、数字センスが無いみたいです。
数字センスがある人であれば、3時間という数字に違和感を感じるようです。
一人で最短で2時間でできてしまう仕事が、3時間と増えるなんておかしい・・・と。
数字的に計算するとすれば、次のように考えられます。
仕事量の全体を100と考えた時に、
Aさんは、1時間で、50(1/2)の仕事量をこなせます。
Bさんは、1時間で、25(1/4)の仕事量をこなせます。
2人の作業で、1時間で75の仕事をこなすことができる。
残りの25を2人でこなすのに、
1時間でできる仕事量 ÷ 75(残りの仕事量) = 1.333...時間
1時間 + 1.333...時間 = 2.333...時間
これが正確な2人でどうじに作業をして仕事を完了させることができる時間になります。
この数字がおかしいという事に気がつけるかどうかが、数字センスそのもののようですね。
数字センスというのは、生まれつきの本能などではなく、
その人の置かれた環境によって磨かれていくので、
何歳からでも数字センスは高めることができるようですよ。
3. コトバ遊び
数字センスを磨きたければ、「表現センス」を磨く必要があるようです。
数字とはコトバと同じで、コミュニケーションと考えた方がいいみたいです。
書籍では、「コミュニケーション」と「思考」を比較して、
コミュニケーションの方が重要とされています。
数字とのコミュニケーション能力を磨く事で、数字センスがどんどん身についていくという事ですね。
ゴミを片付けられない人に、
「いらないものを、ダンボールに詰めてください」
というよりも、
「このダンボール1箱分を捨ててください」
といった方が、ゴミが捨てやすくなるようです。
これは、広さを表す「東京ドーム○個分」とか「ビタミンCがレモン○個分」と言われる事がなんとなく理解しやすい心理を利用しているコトバ遊びと同じです。
こうした、相手に伝わりやすい数字の表現方法を考える癖をつけることは、数字コミュニケーションにおいて重要ですね。
4. 数字遊び
そもそも、数字を計算する時に必ず扱う「四則演算」というのは、誰もが理解していると思いますが、それぞれどういう意味かを説明するのは難しいようです。
筆者は次のように表現していました。
+ : 足し算とは、まとめる時に使うもの。
− : 引き算とは、比べる時に使うもの。
× : 掛け算とは、効率よくまとめる時に使うもの。
÷ : 割り算とは、質を測る時に使うもの。
これを元に、身の回りの数字の並びをあそびにする、四則演算遊びを提唱しています。
車のナンバープレートの4つの数字を四則演算を使って、好きな数字になるように計算式を作るとか、
お店で買い物をした時にもらったレシートに書かれている数字を使って、締めた数字になる四則演算での計算式を作るなど。
ルールは自分で好きに考えてみたい。
この四則演算遊びは、1分程度でできる上、頭の中で考えるだけでできるようにすると、いつでもどこでもできてしまうスマホゲームよりもエコで手軽な思考遊びなんです。
この遊びを習慣化できた人は、数字センスが爆上がりするでしょう。
5. 最強の環境構築
自分の机の上に、手頃な電卓を用意するのがいいようですね。
スマホの電卓アプリよりも、計算だけできる電卓の方が筆者はオススメのようです。
日頃から、大きな数字や、99よりも大きい数字などの複雑な計算は、電卓を叩くクセをつけることで、
結果数値が見慣れた数字に思えてくる環境が作れます。
これらを見て、迷いなくAmazonで12桁のボタン大きめの電卓を買っちゃいました。
あとがき
この本の巻末に、「文系だから・・・という言い訳言葉をいうのをやめましょう。」と書かれていました。
確かに、ビジネス現場で、プログラミングのしている人は
理系で、営業などは
文系という事をよく聞きます。
でも、実際の営業現場は、かなり数字計算をすることが多いし、プログラミングはドキュメントを書くことの方が重要視されていることを考えると、
この文系ってどんなジャンルなんやろ?と、確かに疑問に思いますよね。
そもそも、プログラミングをプロとしてやっている自分も、元々は絵描き志望のデザイン系だった事を考えると、何系は全く属性分けするには乏しいジャンルであるとも言えますね。
とにかく、この書籍、書いてあることは全てよくわかる事ですし、数字センスを上げるための習慣術などが解説されているので、これまでモヤモヤしていた事が少しまとまった思考になりましたね。
 数字が苦手な人のための本なんだけど、数字が苦手と思い込んでいる人はなかなか手が出しずらいタイトルのようにも思えます。
でも、この書籍は学術的とかの内容ではなく、数学が苦手な人でも、数字を好きになるコツというか、周辺の環境作りについて書かれていて、これまで読んだことのある数学系の本で一番読みやすく、もっともスピード早く読み終えることができました。
数字が苦手な人のための本なんだけど、数字が苦手と思い込んでいる人はなかなか手が出しずらいタイトルのようにも思えます。
でも、この書籍は学術的とかの内容ではなく、数学が苦手な人でも、数字を好きになるコツというか、周辺の環境作りについて書かれていて、これまで読んだことのある数学系の本で一番読みやすく、もっともスピード早く読み終えることができました。


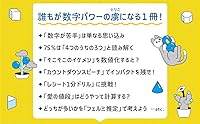











0 件のコメント:
コメントを投稿