
東京工業大学が行なっているエンジニアリングデザイン研究会というのに参加して、EDPについて少しだけ教えてもらうことができました。
EDPとは何かと言うと・・・
Engineering Design Project の頭文字をとっているんだと思いますが、Wikipediaで"EDP"と調べると別の意味が出てきてしまいますね。
でも、EDPって「エンジニアリングデザインプロジェクト」という事で話を進めます。
Googleなども進めているデザインスプリントという書籍やイベントなどもあり、知っている人の間では盛り上がっている様です。
EDPについて
EDPは大学院などの教育コースで用いられることが多い様ですが、色々な分野の人が集まって、課題をクリアして、ものつくりをしていくという工程で、ビジネスの場で使う事を前提としているケースが多い様です。
本来の目的はチームビルディングなのかもしれませんが・・・
ビジネスの場で、新規事業立ち上げや、組織組み立てなど、重要だがあまりしっかりできている会社は少ない中、大学側から社会人などを招き入れて学生とともにものつくりを行うプロジェクトを1年間行なっている様です。
そしてすでに何回かローテーションしており、ツールキットなどもかなり更新されているようですよ。
ようするにEDPは、ものつくりの原点であるという事を把握する教材のようです。
企業の研究開発部門や、新規事業開拓部門の人が結構参加している感じの研究会だったのですが、僕が参加した目的は、「チームビルディング」と「イントラプレナー」という社内起業家を表す比較的新しい言葉の詳細を少し知りたくて参加してみました。
EDPってどうやってやるの?
実際にEDPの講義を聞く会ではなく、初回だったので、前回の経験者が登壇して、自分のやってきたことや価値観を話す場でした。
でも、2名の発表を聞いて理解できたことは、「エンジニアリングデザインは、マーケットイン思考である」という事です。
ものつくりをする上でプロダクトアウトに陥ってはいけないという事を、それぞれの工程で理論化して、作る資料などもツールキットとして用意されているほどの学問になっているようです。
確かに会社内でこうしたツールキットを使えば、もっと簡単に新規ビジネスの構築を絵にかけるのだが、我流でやってる人が多い上、こうした手順を嫌がる人も多いのも事実。
こうした研究会に参加して、きちんと思考を持った人の話が聞けたのはラッキーだったかもしれません。
そして、実際には、ものを作って完了するわけですが、EDP研究会では、合言葉の様に"Tongible"(タンジブル)という言葉が使われていて、意味は「手に取れるもの」を大事にするという事であって、IoTのUI/UXのような意味だと考えるのが分かりやすいと感じました。
そして、いくつかの専門分野の人たちが集まって行う作業であるがゆえに、チームビルディングは欠かせないのだそうです。
それぞれのチームに分かれて、色々な企業からのミッション(お題)に着手していくのだそうですが、それを1年を通してモックアップフェイズから、ロンチまで、まさに仕事さながらで学生と混じって毎週土曜日に行う様です。
なかなか肝が座らないとこうした研究会には参加できないことがよくわかりました。
ツールキットは使う価値あり
そして、この研究会に参加して最も得られた収穫は、「EDPツールキット」をいただけたことです。
とくに制限なく、下記のURLからダウンロードできるのですが、詳細は、実際に教授たちに話を聞かないとわからないことが多すぎるかもしれませんね。
https://titech-edp.github.io/toolkit/

僕が個人的に最も気に入ったのは、「Refrective Action Sheet」というもので、下記からPDFがダウンロードできます。
https://titech-edp.github.io/toolkit/reflective-action-sheet.pdf

このような感じのシートですが、これは、作成するものや課題解決の手段について、「何故あなたがのですか?」「どうして今やるのですか?」「課題はなんですか?」と言った、結構根本的だけど、作り出すものの説明にもなり、詳細を書き出すシートになっています。
これって、ビジネスの現場でまさに役に立つシートで、資金調達に困っている社長さんなどは、自分の会社の製品やサービスをこのシートに書き出してみるだけで、かなり思考が整理されるということに気がつきました。
本来の目的に近い使い方ですが、こうしたツールキットを用意してくれていた日本工業大学の方に感謝いたします。
そして、他にも、「9-window tool」という小規模なアイデアに対して、未来的に拡大路線を描く為のシートなどもあり、非常にビジネスでの活用シーンが満載でした。
僕は毎週土曜日に研究会に参加する事はありませんが、いただいたツールキットをしばらく個人的に使って見て、関係者にフィードバックしてみたいと思います。
 東京工業大学が行なっているエンジニアリングデザイン研究会というのに参加して、EDPについて少しだけ教えてもらうことができました。
EDPとは何かと言うと・・・
Engineering Design Project の頭文字をとっているんだと思いますが、Wikipediaで"EDP"と調べると別の意味が出てきてしまいますね。
でも、EDPって「エンジニアリングデザインプロジェクト」という事で話を進めます。
Googleなども進めているデザインスプリントという書籍やイベントなどもあり、知っている人の間では盛り上がっている様です。
東京工業大学が行なっているエンジニアリングデザイン研究会というのに参加して、EDPについて少しだけ教えてもらうことができました。
EDPとは何かと言うと・・・
Engineering Design Project の頭文字をとっているんだと思いますが、Wikipediaで"EDP"と調べると別の意味が出てきてしまいますね。
でも、EDPって「エンジニアリングデザインプロジェクト」という事で話を進めます。
Googleなども進めているデザインスプリントという書籍やイベントなどもあり、知っている人の間では盛り上がっている様です。
 僕が個人的に最も気に入ったのは、「Refrective Action Sheet」というもので、下記からPDFがダウンロードできます。
https://titech-edp.github.io/toolkit/reflective-action-sheet.pdf
僕が個人的に最も気に入ったのは、「Refrective Action Sheet」というもので、下記からPDFがダウンロードできます。
https://titech-edp.github.io/toolkit/reflective-action-sheet.pdf
 このような感じのシートですが、これは、作成するものや課題解決の手段について、「何故あなたがのですか?」「どうして今やるのですか?」「課題はなんですか?」と言った、結構根本的だけど、作り出すものの説明にもなり、詳細を書き出すシートになっています。
これって、ビジネスの現場でまさに役に立つシートで、資金調達に困っている社長さんなどは、自分の会社の製品やサービスをこのシートに書き出してみるだけで、かなり思考が整理されるということに気がつきました。
本来の目的に近い使い方ですが、こうしたツールキットを用意してくれていた日本工業大学の方に感謝いたします。
そして、他にも、「9-window tool」という小規模なアイデアに対して、未来的に拡大路線を描く為のシートなどもあり、非常にビジネスでの活用シーンが満載でした。
僕は毎週土曜日に研究会に参加する事はありませんが、いただいたツールキットをしばらく個人的に使って見て、関係者にフィードバックしてみたいと思います。
このような感じのシートですが、これは、作成するものや課題解決の手段について、「何故あなたがのですか?」「どうして今やるのですか?」「課題はなんですか?」と言った、結構根本的だけど、作り出すものの説明にもなり、詳細を書き出すシートになっています。
これって、ビジネスの現場でまさに役に立つシートで、資金調達に困っている社長さんなどは、自分の会社の製品やサービスをこのシートに書き出してみるだけで、かなり思考が整理されるということに気がつきました。
本来の目的に近い使い方ですが、こうしたツールキットを用意してくれていた日本工業大学の方に感謝いたします。
そして、他にも、「9-window tool」という小規模なアイデアに対して、未来的に拡大路線を描く為のシートなどもあり、非常にビジネスでの活用シーンが満載でした。
僕は毎週土曜日に研究会に参加する事はありませんが、いただいたツールキットをしばらく個人的に使って見て、関係者にフィードバックしてみたいと思います。

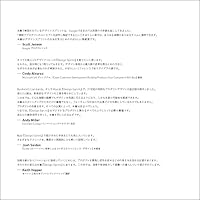
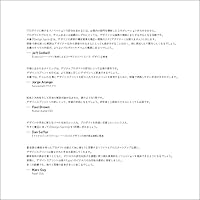


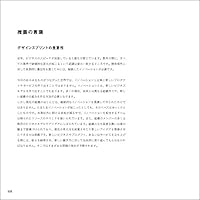
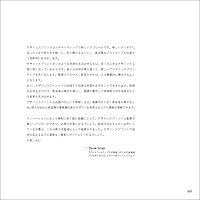










0 件のコメント:
コメントを投稿