
ITスクール講師の仕事をやっていると、「教えてもらうだけスタンス」の生徒にかなり困ることが多いです。
教わった事以外は教えてもらっていないと開き直る生徒ですね。
こういうタイプの生徒は応用が効かない事が多く、わからない時に諦めやすいという性質に気がつきました。
教える側のスタンスとしては、「応用問題」というのは、非常に重要な学問のひらめきであるため、基本を教えて課題として基本を少しだけ難しくしたり、いくつかの基本を組み合わせるような問題にすることがありますが、「組み合わせ方を教わっていない」と踏ん反り返る生徒は実際問題存在します。
これは仕事においても、新人教育をやっている担当者の人も経験したことがあると思いますが、かなりのモンスター生徒である場合もあります。
生徒に悪気がある場合は、モンスターなのですが、悪気がなくこういう性質を持っている人は、それも含めて教育してあげる必要があるのですが、教え方一つでこうした生徒さんも非常に上達するといういい事例を知ったのでご紹介します。
褒めちぎる教習所
三重県にある南部自動車学校は、教員が受講生の人を徹底的に笑顔で褒めることで、運転技術の向上から、その後の事故発生率を軽減させることに成功した教習所です。
生徒さんは、みな教習所の先生と、非常に強い信頼を持つことができ、卒業するときに非常に自信に満ち溢れるとのことです。
義務教育の学校や、仕事現場でも、この法則を使えば、先生と生徒の信頼関係から成績アップや、上司と部下の信頼関係からの売上向上、などなど、誰もが損しない構造を作ることが可能なのではないでしょうか?
実はこのやり方というのは「ピグマリオン効果」という心理効果をうまく使っているという点に注目してみましょう。
ピグマリオン効果とは
簡単に言うと、教えている人が成績向上を期待する事を、信頼関係に伴って生徒側がそれを裏切らないように結果を出す効果とのことです。
学生時代に、自分の偏差値よりも高い学校を受験しようとする場合、親が反対しても、先生ができると言ってくれたので、頑張ってトライして合格したというような場合、ピグマリオン効果が働いたと考えられます。
教わる側で考えると、「やればできる子」と先生が言ってくれるのって非常にうれしいし、実際にやってみたくなりますよね。
こうした事ができる先生が、後に生徒から慕われていい人生が送れるという事は誰が考えてもわかります。
しかし、実際の教育現場では、できる子を褒めてできない子は少し冷たい目を向ける教師が多く、ピグマリオン効果が実践できている先生が少ないと言う実態もあるようです。
ちなみに、この効果の反対で、教師が期待しなくて、生徒の成績が下がってしまう事を「ゴーレム効果」と呼ぶそうです。
期待する事で物事は好転する
実際に人に対して褒める事、期待する事は、どのくらい難しいのでしょうか?
先生であれば、できない子に「やればできる」「期待している」と言い続けるだけでピグマリオン効果は生まれるのでしょうか?
実際にはこんなに単純ではない事でしょう。
「やればできる」という言葉には根拠が必要であり、仕事で上司が部下に対して「やればできる」と言って、レベルの高い仕事を割り振った場合、部下は「できるわけがない」という思考に偏ってしまいがちですが、
ここに「君の特技の◯◯を使えばできる」ときちんと根拠を示してあげれば、本人からしてみたら「できるわけがない」から「やればできるかもしれない」という気持ちになります。
そこに「社内にキミしかいない」というさらなる根拠を付け加えると、本人としては、「自分がやらないとダメだ」という心理になり、少し厳しい課題であっても、頑張って乗り越えようとするわけです。
ここには、上に立つ人の信頼という事をきちんと伝えている事が、単なる言葉で軽く言っているのとは違いきちんと部下に向き合っているという姿勢が大事であると言えます。
部下が仕事に失敗した時や、子供がいたずらをしてそれを叱る親、バイト先で失敗した時に店長から怒られた事、など、上に立つ人は「叱る」という行動をする事が単なる間違いである事もピグマリオン効果を考えると、本人に分からせるべき行動は何かと考えてみる必要があると思われます。
教える側がやべき事は信頼関係構築
要するに人と人は信頼関係で結ばれており、上の人が下の人を伸ばそうとする意欲はこの信頼関係を強く築けるかどうかに掛かっていると考えても良さそうです。
できない部下や生徒に対して、叱っても何も良い事がないのですが、先生が諦めた様な表情を浮かべているかもしれませんね。
今回は先生側、上司側の考えるべき内容で、生徒はいかにやる気を伸ばしてもらえるかを期待してみてもいいかもしれないという話でした。
ちなみに、「ピグマリオン効果」は別名で、「教師期待効果」や「ローゼンタール効果」とも言われていますよ。
気になる人は調べてみると面白い発見があるかもしれませんね。
 ITスクール講師の仕事をやっていると、「教えてもらうだけスタンス」の生徒にかなり困ることが多いです。
教わった事以外は教えてもらっていないと開き直る生徒ですね。
こういうタイプの生徒は応用が効かない事が多く、わからない時に諦めやすいという性質に気がつきました。
教える側のスタンスとしては、「応用問題」というのは、非常に重要な学問のひらめきであるため、基本を教えて課題として基本を少しだけ難しくしたり、いくつかの基本を組み合わせるような問題にすることがありますが、「組み合わせ方を教わっていない」と踏ん反り返る生徒は実際問題存在します。
これは仕事においても、新人教育をやっている担当者の人も経験したことがあると思いますが、かなりのモンスター生徒である場合もあります。
生徒に悪気がある場合は、モンスターなのですが、悪気がなくこういう性質を持っている人は、それも含めて教育してあげる必要があるのですが、教え方一つでこうした生徒さんも非常に上達するといういい事例を知ったのでご紹介します。
ITスクール講師の仕事をやっていると、「教えてもらうだけスタンス」の生徒にかなり困ることが多いです。
教わった事以外は教えてもらっていないと開き直る生徒ですね。
こういうタイプの生徒は応用が効かない事が多く、わからない時に諦めやすいという性質に気がつきました。
教える側のスタンスとしては、「応用問題」というのは、非常に重要な学問のひらめきであるため、基本を教えて課題として基本を少しだけ難しくしたり、いくつかの基本を組み合わせるような問題にすることがありますが、「組み合わせ方を教わっていない」と踏ん反り返る生徒は実際問題存在します。
これは仕事においても、新人教育をやっている担当者の人も経験したことがあると思いますが、かなりのモンスター生徒である場合もあります。
生徒に悪気がある場合は、モンスターなのですが、悪気がなくこういう性質を持っている人は、それも含めて教育してあげる必要があるのですが、教え方一つでこうした生徒さんも非常に上達するといういい事例を知ったのでご紹介します。
 ITスクール講師の仕事をやっていると、「教えてもらうだけスタンス」の生徒にかなり困ることが多いです。
教わった事以外は教えてもらっていないと開き直る生徒ですね。
こういうタイプの生徒は応用が効かない事が多く、わからない時に諦めやすいという性質に気がつきました。
教える側のスタンスとしては、「応用問題」というのは、非常に重要な学問のひらめきであるため、基本を教えて課題として基本を少しだけ難しくしたり、いくつかの基本を組み合わせるような問題にすることがありますが、「組み合わせ方を教わっていない」と踏ん反り返る生徒は実際問題存在します。
これは仕事においても、新人教育をやっている担当者の人も経験したことがあると思いますが、かなりのモンスター生徒である場合もあります。
生徒に悪気がある場合は、モンスターなのですが、悪気がなくこういう性質を持っている人は、それも含めて教育してあげる必要があるのですが、教え方一つでこうした生徒さんも非常に上達するといういい事例を知ったのでご紹介します。
ITスクール講師の仕事をやっていると、「教えてもらうだけスタンス」の生徒にかなり困ることが多いです。
教わった事以外は教えてもらっていないと開き直る生徒ですね。
こういうタイプの生徒は応用が効かない事が多く、わからない時に諦めやすいという性質に気がつきました。
教える側のスタンスとしては、「応用問題」というのは、非常に重要な学問のひらめきであるため、基本を教えて課題として基本を少しだけ難しくしたり、いくつかの基本を組み合わせるような問題にすることがありますが、「組み合わせ方を教わっていない」と踏ん反り返る生徒は実際問題存在します。
これは仕事においても、新人教育をやっている担当者の人も経験したことがあると思いますが、かなりのモンスター生徒である場合もあります。
生徒に悪気がある場合は、モンスターなのですが、悪気がなくこういう性質を持っている人は、それも含めて教育してあげる必要があるのですが、教え方一つでこうした生徒さんも非常に上達するといういい事例を知ったのでご紹介します。

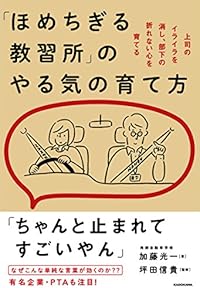










0 件のコメント:
コメントを投稿